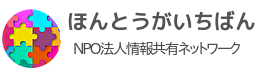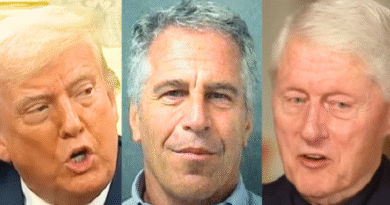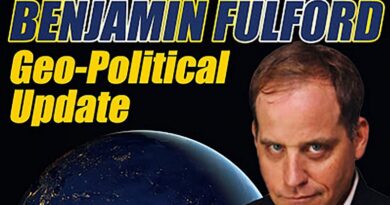中国臓器狩り:肝臓半分で2千万円、中国のSNSで拡散される「日本で臓器募集」投稿が意味するもの
▲ドキュメンタリー「国家所有の臓器」は、中国共産党が認可した生体からの臓器収奪の実態を暴露している。写真はドキュメンタリーの一場面(Samira Bouaou/大紀元)
出典:大紀元|2025/09/12
最近、SNS上で「日本にいるO型、50歳以下の若い男性に2千万円を支払う、肝臓の半分を自発的に提供してほしい」「日本の大手病院で手術、生活に支障なし」という投稿が中国語や中国人コミュニティを通じて拡散している。
こうした募集は、中国系チャットグループやWeChatなどプライベート空間を主戦場に、現実に日本社会の中で展開している。
これは単なる怪しげなネットの噂にとどまらず、日本の非常に細かい点まで整っている移植医療制度や病院名を挙げて信頼感をあおり、リアルな臓器ビジネスが日本の法と社会の抗体をすり抜けつつあることを意味している。
中国移植ビジネス需要の高まりと「日本」の現場
背景には、近年急増する中国側富裕層/権力層の臓器移植ニーズがある。中国国内では法輪功学習者やウイグルなど政治・宗教的マイノリティを対象にした大量の臓器収奪疑惑が国際社会で批判されているが、不信感から安心・高品質の国外移植を求めて日本の医療やSNSを利用した非合法ルートの開拓が進んでいる。
しかも、移植希望の日本人本人の目の前で、具体的な中国人ブローカーやコーディネーターが安くて早い移植を売り込んでくるケースも各地で報告されている。
現場証言で明らかになった中国・日本連携のリアルな取引
「そんなことはありえない。本当にそんな恐ろしい事が起きているのか」と考える人もいるかもしれない。
しかし元暴力団組長で経済評論家の菅原潮氏(猫組長)が体験した2007年の事例は、その闇の裏付けとなる。
菅原氏が中国の臓器ビジネスに関わったのは知人の移植希望患者が中国の武装警察系病院で肝臓移植を受ける手術直前になって、病院側が用意したアルブミンという血液製剤が偽物だと判明したことがきっかけだった。菅原氏はアルブミンを日本で調達し、北京に届けるよう依頼を受けた。
菅原氏は、現地の中国人ブローカーのことや武装警察高官の護送で特別なVIPルートを通れるなど、「中国共産党(中共)の権力の加担なくしてこのビジネスは成立しない」と証言する。
移植前日に「隣の部屋にドナーがいるから見ないか」との誘いを受けた。菅原氏が見た21歳の男性ドナーは、寝たきりで手足の腱を切られ、逃走防止・状態維持のために薬で眠っていた。臓器は生きたまま摘出して最良の状態で提供された。コーディネーターは「死刑囚は法輪功の人間」と明かし、「中国は人が多いから、いくらでも適合ドナーが用意できる」と語ったという。
病院ではサウジアラビア、ドイツ、日本から来た患者が同時期に手術を受けており、菅原氏は「日本人もたくさん来ていると聞いた」と語っている。
中国で行われている生体臓器収奪の現状
中国では毎年6~10万件の臓器移植が実施されていると推計され、その大部分は囚人や政治・宗教的少数派から強制的に摘出した臓器に依存している。主なターゲットは法輪功学習者、ウイグル人、チベット仏教徒、地下キリスト教徒など「良心の囚人」と呼ばれる人々だ。
移植医療の待機期間は海外と比較して非常に短く、1か月足らずでの手術が可能だとうたわれるなど、組織的な斡旋と摘出の存在を裏付ける事例・証言も絶えない。元中国人医師は、軍病院による患者への無断摘出や若い被害者臓器を軍高官が利用するケースを暴露し、事態の深刻さを訴えている。
2006年、アニーと名乗る女性とピーターと名乗る男性の2人の証人がアメリカに亡命し、中共が法輪功学習者から臓器を強制的に摘出していたことを暴露した。
アニーさんは「私の元夫は法輪功学習者から臓器を摘出する手術に携わった。摘出された人の中にはそのまま火葬炉に入れられた者もいる。中国人として本当に心が痛む」と証言した。
アニーさんの証言を受け、カナダの人権弁護士デービッド・マタス氏、カナダの元アジア太平洋州担当大臣デービッド・キルガー氏が独立調査を実施した。52種類の証拠による交差検証の結果、中共による法輪功学習者からの臓器収奪の事実を確認し、大量の移植臓器の出所が依然として説明できないことも判明した。
アメリカの中国研究者イーサン・ガットマン氏の著書『The Slaughter: Mass Killings, Organ Harvesting, and China’s Secret Solution to Its Dissident Problem(大虐殺:反体制派問題に対する秘密の解決策』では、多数の新証拠を提示している。
ガットマン氏は、中共当局による臓器摘出は1990年代末からウイグル族に対しても小規模ながら実施されていたと語る。少なくとも6万4千人の法輪功学習者が臓器収奪の犠牲になったと推計しており、その数は増え続けていると指摘する。
中国の収容所や火葬場の併設、囚人への医療検査と臓器摘出の体系的実施も、海外報道や衛星画像が証明。国際社会は現地調査と証言収集に奔走するが、中国当局は否定・制限・情報隠蔽を続けている。
強権指導者たちの「寿命」への執着
2025年9月3日、北京での軍事パレード前、中共党首の習近平とロシアのプーチン大統領の会話を偶然マイクが拾った中で、臓器移植技術や「150歳まで生きる」ことについて率直に語り合っていた。プーチン氏は「バイオ技術の発展により臓器移植が繰り返し可能となり、不老不死も現実になる」と発言。習近平も「今世紀中に150歳まで寿命の延長の可能性がある」と長寿社会の未来を語った。両首脳とも70代、長期独裁体制を維持し続ける裏には「永生技術」や延命科学への関心が垣間見える。
この対話は国際社会や報道界に波紋を広げ、長期政権維持と倫理、権力の在り方、人類の生存戦略という深いテーマへと拡がっている。
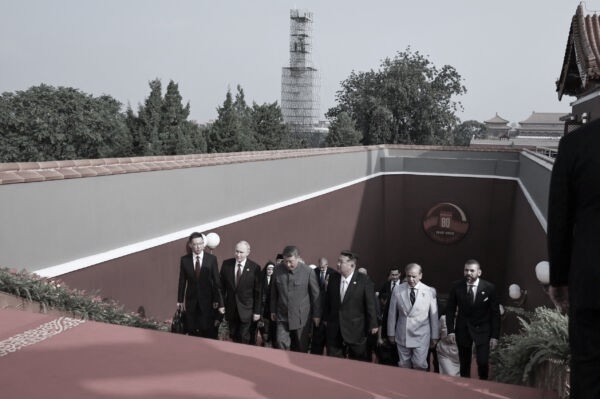
習近平「150歳まで生きる」発言の映像 中共側がロイターに削除要求
習近平が「臓器移植」「150歳まで生きる」と発言した映像について、中国共産党側がロイターに削除を要求した。
国際社会の動きと日本の課題
台湾・イスラエル・イタリア・スペイン・アメリカなどは中国や第三国への渡航移植を規制し、違反には厳罰・刑事罰を科している。だが日本は、患者・医師・仲介者への具体的な規制や監視が遅れており、「金さえあれば移植ができる穴場の国」として中国系コミュニティで認識されつつある。
福祉先進国の日本が、非人道的な臓器収奪ビジネスの安全な抜け道となってしまう現状について、ドキュメンタリー映画や国際人権団体の講演会(そこでの現場証言)で強い警鐘を鳴らしている。